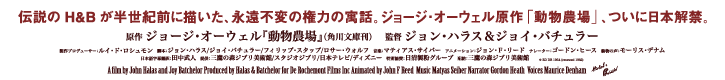Main Contents

「ソビエト神話の正体をあばく」
動物寓話のかたちをとる『動物農場』には実名はひとつも出てこないが、ロシア革命以後のソ連史をふまえているのは一目瞭然だった。オーウェル自身、この物語を書いた動機は、「だれにでも容易に理解でき、他国語にも容易に翻訳できるような物語によって、ソビエト神話の正体をあばく」ことだったと述べている。「ソビエト神話」とは、平たく言えば、「ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)の政治体制について人びとがいだいていた、まちがった思い込み」ということであり、ソ連を階級差別と貧富の差が消えた輝かしい理想の共産主義国とみなす(彼にいわせれば当時の左翼知識人が抱きがちな)幻想を指すものだった。神話化(理想化)のあまり、その暗黒面が見えなかった。その最たるものが「粛清裁判」だった。
一九一七年の三月革命でロマノフ王朝が倒され、十月革命でボルシェビキ(共産党多数派)によりソ連が樹立、その指導者であったレーニンの時代でもすでに共産党の一党独裁が進められていたが、レーニンが表舞台から消えた頃から、スターリン独裁体制の地固めとして、テロとしての「粛清」がじわじわと進んでゆく。レーニン没後の一九二五年には最大の政敵トロツキーを失脚させる。性格的にも対照的なスターリンとトロツキーの役割は、『動物農場』ではそれぞれナポレオンとスノーボールという二頭の豚が演じている。結局トロツキーは党から除名され、国外追放の処分を受ける(最後は一九四〇年にメキシコで暗殺)。物語ではナポレオンが子飼いの猟犬をけしかけてスノーボールを農場から追放するくだりでそれが描かれる。
こうしてスターリンは、ほかにも多くの政敵を排除してゆき、やがて一九三六年の第一次モスクワ裁判に至る。スターリンのかつての同志ジノビエフらが逮捕され、でっち上げられた罪状を認め、裁判がすむとすぐに銃殺刑に処された。これを初めとして、身に覚えのない罪で告発され、ありもしない自白を強要されるという、国家裁判が無数になされる。「人民の敵」を追及する「粛清」という名のテロルは一九三八年までつづき、その数年間に、共産党幹部から農民に至るまで、数百万人が犠牲になったとされる。
この粛清裁判は『動物農場』では、ナポレオンに反抗した豚や鶏が中庭に引き立てられて、スノーボールの手先であったと自白させられる場面で描かれる。自白を終えた彼らは犬に食い殺される。「この動物たちはみんなその場で殺されました。こんなふうにして、告白と処刑はえんえんとつづき、しまいにはナポレオンの足下に死がいの山ができてしまい、血なまぐさい空気がたちこめました。」
このように、ソ連史の重要な局面が『動物農場』のなかに書き込まれている。ロシア革命はもとより、一九二五年以後の第一次五ヶ年計画などの農業集団化計画の破綻(風車建設のエピソード)、三九年の独ソ不可侵条約の締結、その条約を破っての四一年のドイツ軍によるロシア侵攻、そして四三年のテヘラン会談に至るまでの経緯が動物寓話のかたちをとってきっちりと書き込まれている。
そのようなソ連の実態をオーウェルが認識したのはスペイン内戦に参加した経験によるものだった。一九三六年の暮れにバルセロナ入りした彼は、翌三七年初めに民兵組織ポウム(マルクス主義統一労働者党)に入隊。アラゴン戦線の塹壕で冬をすごし、春に一時休暇をえてバルセロナに滞在していたときに、共和国政府側のセクト争いによる市街戦を目撃する。その後アラゴン戦線にもどったが、敵の狙撃で銃弾が首を貫く重傷を受け入院。さらにはポウムに対する共産党の粛清がはじまり、彼の身もあやうくなったが、危機一髪のところでフランスに脱出。これについては、ルポルタージュ文学の傑作である彼の『カタロニア讃歌』(一九三八年)に詳しい。
オーウェルがスペイン内戦に関わったとき、まさにソ連本国は粛清の真っ只中で、その余波をこうむったということになる。ファシズムに対して共に戦っているはずが、自分の所属した民兵部隊が「トロツキー主義者」の名で共産党から迫害され、仲間の多くが投獄されたり殺されたりし、彼自身の命もおびやかされた。その恐怖を身をもって体験したことが、いち早く「粛清」という聞こえのよい名のテロ行為の暴虐さを認識し、ソ連を理想国家と見る「神話」をあばかなければならないと確信させたのだった。そしてこうした批判をオーウェルはあくまで自身の信奉する「民主的社会主義」としての立場からおこなっていたのである。