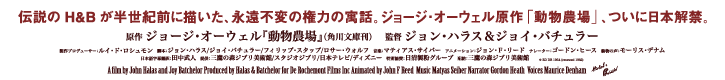Main Contents

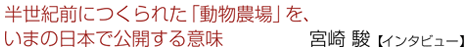
―「動物農場」との出会いから聞かせてください。
ハラス&バチュラーの「動物農場」が、ぼくの記憶にとどまっていたのは、ジョン・ハラスがつくったアニメーション技術の本があるんです(『アニメーション─理論・実際・応用─』ジョン・ハラス、ロジャー・マンベル著、伊藤逸平訳、東京中日新聞出版局、一九六三年)。ぼくがアニメーションの仕事をはじめたのは一九六三年ですが、そのころアニメーションの技法書といったら、このジョン・ハラスの本と、あとはロシアの本くらいしかなかったんです。ロシアの本はあまり役に立つことはなくて、ただ一点だけ、「言語的に面白いものが、映像的に面白いとは限らない」という教訓が書いてあって、それだけは印象に残ってるんですが。
ジョン・ハラスの本は、撮影上のことやら作画上のことやら、いろんなことを含めて自分たちの経験を盛り込んだ、ぶ厚い本でした。そのなかに「長編アニメーション」という項目があって、「長編アニメーションをつくる者たちは、いままで誰も耕したことのない石ころだらけの荒地に鍬を打ち込むような思いを味わうだろう」というようなことが書いてあったんですよ。「動物農場」をつくった後にこの本を書いていますから、彼ら自身がそんな思いを味わったということですよね。「動物農場」は、商業的にはみごとに失敗したんです。
長編アニメーションというのは、第二次世界大戦が終わって、五〇年代に入る頃にあちこちでつくられるようになります。フランスでは「やぶにらみの暴君」(ポール・グリモー監督、一九五三年。一九八〇年には作者完成版「王と鳥」として公開)、ロシアでは「せむしのこうま」(イワン・イワノフ=ワノ監督、一九四七年。のちに「イワンと仔馬」に改題)や「雪の女王」(レフ・アタマーノフ監督、一九五七年)という傑作がつくられ、そしてイギリスでつくられたのが「動物農場」だったわけです。もちろんアメリカではウォルト・ディズニーがすでにたくさんの長編アニメーションをつくっていましたが、技術的にあまりにも自分たちとかけはなれているので、どう学んでいいのかわからない(笑)。それとくらべると、「やぶにらみの暴君」や「雪の女王」のほうが、技術的にも心情やテーマの部分でも、自分たちに引き寄せやすかったんですね。ですから、ぼくらの世代にとっては、長編アニメーションをつくりたいと思ったときに、お手本としていくつかあるなかの一本だったんです。
だけど、ジョン・ハラスの本を読んでから実際に「動物農場」を見るまでには、もう少し時間がかかりました。たまたまテレビでやっているのを見たんですけど、「よくこんなものをつくったな」と思いました。子供たちが見ることを前提につくったものではないんです。
―当時としては珍しい、大人向けの長編アニメーションですね。
当時のイギリスは、第二次世界大戦が終わり、冷戦が始まろうとしているときです。第三次世界大戦が始まるんじゃないか、原爆の戦争が始まるんじゃないかという恐怖、と同時に、恐ろしい勢いでふくらもうとするソ連があって、世界中がソ連型の共産主義になったら大変だ、という危機感が強かった。
ジョージ・オーウェルはまさにそれを考えて、『動物農場』や『一九八四年』という作品を書いたんですよね。それは、ハラス&バチュラーも同じ気持ちだったと思います。ハラスはハンガリー出身のユダヤ人ですから、推測するに、ハンガリーからイギリスへ亡命した人でしょう。自分たちの祖国は、戦時中はナチスドイツの、戦後はソ連の支配下にあった。まさに『動物農場』で描かれているような、独裁者が君臨している全体主義的な世界にリアリティがあったんです。彼自身にとって、ものすごく今日性のあるテーマだった。だからこそ、この映画をつくろうと思ったと思うんです。口ではうまいことを言いながら、まじめな人間たちをこき使って、自分は権力の上にあぐらをかいている、そういう人間の醜さをえぐり出したいと思ったんでしょう。
だけど、搾取とか収奪というのは、なにも共産主義だけにあるんじゃなくて、資本主義はまさにそういう「しくみ」です。ぼくは会社というのは、誰よりもそこで生活しながら仕事している人間たちの共有の財産だと思っています。でも、それは社会主義的な考え方なんですね。いま、主流になっている考え方というのは、私有財産として株をもっている人間のほうに発言権があって、株主たちが「この経営者はダメだ。もっと儲ける経営者を選べ」といったら、経営者はどんどん変わらなきゃいけないとか、そういうアメリカ型の資本主義です。それを進めていくと、リストラをして正社員を減らして、派遣社員やアルバイトだらけにして、労働基準法のギリギリまでこき使ってポイッと捨てる。正社員は正社員でくたくたになって働いてる。いくらでも替わりはいるんだという、いまのしくみこそ、「動物農場」と同じです。
これがこの世のなかのしくみだというのは、ある時代までは常識だったんです。だけど、いつのまにか、みんなそれを忘れてしまってたんです。みんなが中産階級だと思いこむことによって、搾取の構造というのは見えなくなっていた。と同時に、戦後の日本の経済成長のなかでは、経営者も必死に働かないといけなかったし、日本は累進課税で、トップと末端の所得格差が少ない国だったんですよ。バブルの前までは、そういう社会が一時あったんです。だから支配や搾取の構造には、リアリティが薄くなっていたんですよ。少しは平等感のある社会になってきたと思ったら、バブルで足をすくわれて全部崩れた。終身雇用制もあっというまに捨てたし、年功序列も捨てた。そして能率給だとか、目標設定するとかってやりはじめた。能率給なんかにしたら、神経症になるだけだと思いますけどね。ふつう才能があるのなら、損得はあとまわしで力をつくして仕事をするのは当然で、金のために仕事するなって。いや、金のために働かなきゃいけないんだけど、そういう考え方は自分を貶めることになりますから。まあ、いろんな考えがありますが、ぼくたちは「仕事は人生の伴侶だ」ということでやるものと思い、そうしてきました。
しくみのなかでは自分だってナポレオンなんだ
―この映画のなかでも、農場主を追い出した後、動物たちが助け合って仕事を分担する場面では、働く喜びが描かれています。
この映画に出てくる豚のナポレオンのように露骨にずるい強欲な独裁者がいて、それがひとりでうまいものを食っていて、民衆はひどいものを食いながら骨身を惜しまず働かないといけないというしくみよりは、現実はもう少しまわりくどいですね。ナポレオンのような憎々しい十九世紀的な資本家というのはもういないし、痩せ衰えた馬だって、うちに帰ってきたらインターネットで株の取引をやってるとか、そういうふうになってますよ。
まじめに働くよりも、インターネットでちょこちょこっと株をやったり、人がつくったものをどこかに移して簡単にお金を儲けるとか、そういうのがいちばんカッコいい生き方だ、というふうに思ってる人が増えちゃった。要するに、「みんなでナポレオンになろう」みたいな社会になっちゃったんですよ。「ナポレオンになれないのは、自己責任だ」といわれてしまう。ごくふつうの人たちがナポレオンになってるんです。怠け者のナポレオンもいるけど、勤勉なナポレオンだっていますからね。ナポレオンじゃなくても、ナポレオンに使われている小ナポレオンなんです。
もっと身近なことで言うと、日本のアニメーションのことを「ジャパニメーション」といってるけど、じっさいには中国や韓国のアニメーターたちによって支えられています。中国の人たちに仕事を頼む日本人が、たとえどんなに善意をもっていて、なるべく日本国内と同じ金額を払うとか、ちゃんと技術指導をしてあげようと思っているとか、そういうことがあったところで、向こうから見たら高級ホテルに泊まって、そこから通ってくる人間が自分たちの上に君臨していることに変わりはないんです。そこにあるのは露骨な賃金格差です。そして中国人がいくら意欲をもっていても、日本人に向かって「おまえさんの仕事を、わたしが変わりにやるよ」というのができないしくみが、厳然とそこにあることを忘れちゃいけないんです。ところが、そういうところを見ないようにして、みんな平等で同じようにチャンスがあって、チャンスをものにできないのは自己責任だ、みたいなことになっている。
自分が善意であるからといって、自分が善良な存在だとは思ってはいけない。とくべつお金を稼いでいるとか、楽をしているわけじゃないから、自分は無罪だ、とは思ってはいけないんです。しくみのなかでは、自分だってナポレオンなんです。そのしくみの問題はいっぺんには解決できないですけど、だからといって、手をこまねいて、無関心でいられること自体、すでにそれはナポレオンなんだってことなんです。個人的なことだけじゃなくて、社会における位置とか役割によって、自分の存在の本質には、いつも気づいていなくちゃいけません。
半世紀以上も前につくられた「動物農場」をいま公開する意味は、ここにあるんです。社会にはしくみがあるということ。複雑になってはいるけど、でも根源には、労働者がいて収奪者がいるという、そのしくみは変わってないんです。それを知るうえでは、この「動物農場」には意味があると思います。小林多喜二の『蟹工船』と同じように。蟹工船というのは、ひとつの隔絶した世界だから、国家の意味とか社会のしくみということを図式的に描きやすいし、「動物農場」も、世界の縮図として、寓話として描かれているわけですよね。
―映画を観ているときは、酷使される馬のほうに感情移入していますが、じつは自分だって利己的な豚のほうなんだということを忘れてはいけないですね。
ぼくが映画化するとしたら、もっとナポレオンを複雑に描くと思います。ナポレオンがはじめからずるくて卑怯なやつなんじゃなくて、むしろ、ひじょうにまじめに改革をやりながら、やってるうちにだんだん、人に言われたことを疑いもなく信じているだけの愚鈍な動物たちがいやになってきて……というキャラクターとしてナポレオンを描いてくれたら面白かったのに、と思います。人間はそんなに単純じゃないと思いますから。
パラダイスは地球とその周辺にはない
―この映画を観たあとには、社会主義的な意識に目覚めます。いまこそ民主的な社会主義が見直されるべきではないか、と。
独裁者がいなくて、みんなでそこそこ幸せにやっていくことができるようにするには、どうしたらいいのか。それにたいする人類の最大の賭けが、社会主義だったんですよ。十九世紀にヨーロッパのなかで育てられて二十世紀にかけて実験した結果、見事に敗北したんです。楽園は地上にはないんです。
ぼくは、楽園というのは、幼年時代にしかないと思います。幼年時代の記憶に、楽園はあるんだと。楽園をつくろうという運動はいつもあるけど、かならず挫折するのはそれなんです。だから、「この世は楽園じゃない」ということで生きるしかないんです。ただ、それではあまりにしんどいから、バーチャルなもので気をまぎらわせながら生きる方法を人類は編み出したんですよね。
だけど、そこには、「パラダイスは地球とその周辺にはない」という現実認識がいるんです。一九七〇年くらいに、スウェーデンの経済相が日本にきて短い講演をしたんですよ。ぼくはそれをテレビで見ていて、ひどく胸を打たれたんですけど、「パラダイスは地球とその周辺にはありません。それを認識したうえで、国家のできること、国家の役割を考えなければいけません」と。そのリアリズムに感心しました。リアリズムを失うと、国家はとんでもないまちがいをやる。日本の軍閥政治の数十年間のまちがいは、リアリズムを失ったのが原因です。
ヨーロッパが社会主義に絶望したのは、一九三六年、スペイン内戦のときです。スペイン内戦では、社会主義者だけではなく、無政府主義者も、民主主義者も、いろんな勢力が人民戦線に集まったわけですね。そのときにソ連に裏切られたというのが、ジョージ・オーウェルの大きな体験だったわけです。裏切られた革命というかたちで『カタロニア讃歌』を書いた。ソ連の実態を知るにつけ、多くの進歩的な青年たちは、社会主義に挫折していきました。
それでも、なんとかして民主的な社会主義がありえないかというのは、戦後、イタリアやフランスに残っていた共産主義者たちを支えていたものなんです。結局、たどりついたのはEU(欧州連合。European Union)です。それは社会主義者がつくったものではないけれども、ヨーロッパが生き延びるとしたらEUしかない。
民主的な社会主義はつくれるのか。つくれるとしたら、グローバリズムとは正反対のところにあるとぼくは思います。それは地産地消(地域生産地域消費の略。その土地で生産されたものをその地域で消費すること)です。スローフード、スローライフのような波は、くりかえしくりかえし、おこりますけど、そのあらわれなんですよ。
人間の欲望はコントロールしないといけないんです。人間の欲望を増大していっていいんだという考え方は、地球が有限であるということがわかった瞬間から、変わるはずなんですよ。
ぼくのいまの願いは、自分の下着を国産にしたいってことです(笑)。お金を出せば、いろいろあるのかもしれませんけど、なるべくつつましく暮らしたいと思っている人間にとって、手ごろな値段の下着はみんな中国産でしょう。さっきのアニメーションの話と同じで、露骨な賃金格差の構造がある以上、それもやむをえないのかもしれない。だけど、一方で、自分の住んでる町内に靴屋さんがあって洋服屋さんがあって、下着もそこでつくってもらえたら、どんなにいいだろうと。「あんた腹出たね、まずいね」っていわれながら(笑)。子どもが学校を出ても、何をしていいのかわからないっていうんじゃなくて、「あそこの洋服屋の丁稚になりなよ」って。そういうふうに地産地消でやっていけて、激しく変化していかない時代がつくれないかなと。ぼくなんかは夢見るだけですよ。それはもう無謀な夢かもしれません。
でも、「動物農場」は最後にいってるわけですね。「何度でも立ち上がる権利がある」って。この映画のラストシーンは、原作の結末にさらに付け加えたものですが、「人民はくりかえし、立ち上がり続けるんだ」というところで終わっている。ぼくも、それしかないと思います。
―結末の改変については批判もあるようですが、ジョン・ハラスは、「見る人に未来への希望を与えたかった」と語っていたそうです。
そうだと思います。同時に、クーデターなり革命をおこして独裁者を追い出して、理想の社会を実現しようとしても、結局、気がつくとまた次の独裁者があらわれる、というのも、人間の歴史を見ればわかることです。それでもやっぱり立ち上がらざるをえないんです。
つまり、反乱する権利はもっている。ぼく自身、六〇年代には労働組合の活動をずいぶんやりました。べつに自分たちのやったことが良いことだとか悪いことだとかいうつもりはないけど、人間はいつでも愚行をおかす危険があるってことをわかりながら、それでもなにもやらないよりは、やったほうがいいと思います。最近になって、若い人たちがまた独立系の労働組合をつくったりしているようですけど、いろんなところで立ち上がって革命をおこしたほうがいいんです。
―じつはこの映画化にはCIAが関与していて、資金を提供していたという事実もわかっていますが。
CIAがかかわっていたかどうかなんて、ぼくにとっては、どうでもいいことです。ハラス&バチュラーは、誰のお金でもいいからつくりたかったんですよ。だと思います。蛇口はなんでもいい。出てきた水を使って、つくれるものならつくる。そういうふうになる可能性は、ぼくも十分にもっていますから。
「動物農場」がすばらしい作品か、傑作かといわれたら、そこまでの作品ではないと思う。つまり、ぼくがいったような人間の複雑さを描くことにおいて、不徹底だと思うんです。不徹底ではあるけれど、見ておいても悪くはない映画です。
技術的には、いま見ると、つたないけれども、つたないところも含めて、とてもよくわかる。苦闘したんだと思うんです。長編アニメーションをつくるということは、あの時代、どれほどの覚悟が必要だったか。CIAの資金だけで判断しちゃいけない。そしたら軍閥政治の日本に生きて、そこでごはんを食べていた人たちはみんな薄汚れていたのか、というのと同じです。最初にもいったように、ハラス&バチュラーにとって、この映画をつくることは切実な問題だったんだと思います。CIAの金をうまく使って、結果的に、自分たちのつくりたいものをちゃんとつくったということだと思いますね。
宮崎 駿
アニメーション映画監督。1941年1月5日、東京生まれ。
1963年、学習院大学政治経済学部卒業後、東映動画(現・東映アニメーション)入社。「太陽の王子ホルスの大冒険」('68)の場面設計・原画等を手掛け、その後Aプロダクションに移籍、「パンダコパンダ」('72)の原案・脚本・画面設定・原画を担当。'73年に高畑勲らとズイヨー映像へ。日本アニメーション、テレコムを経て、'85年にスタジオジブリの 設立に参加。その間「アルプスの少女ハイジ」('74)の場面設定・画面構成、「未来少年コナン」('78)の演出などを手掛け、「ルパン三世 カリオストロの城」('79)では劇場作品を初監督。雑誌「アニメージュ」に連載した自作漫画をもとに、'84年には「風の谷のナウシカ」を発表、自ら原作・脚本・監督を担当した。
その後はスタジオジブリで監督として「天空の城ラピュタ」('86)「となりのトトロ」('88)「魔女の宅急便」('89)「紅の豚」('92)「もののけ姫」('97)「千と千尋の神隠し」('01)「ハウルの動く城」('04)といった劇場用アニメーションを発表している。
中でも「千と千尋の神隠し」では第52回ベルリン国際映画祭 金熊賞、第75回アカデミー賞 長編アニメーション映画部門賞などを受賞しており、「ハウルの動く城」では、第61回ベネチア国際映画祭でオゼッラ賞を、続く第62回同映画祭では、優れた作品を生み出し続けている監督として栄誉金獅子賞を受賞している。
現在は、4年ぶりの最新作「崖の上のポニョ」を全国東宝系で公開中。
著作に「トトロの住む家」「シュナの旅」「何が映画か」(黒澤明氏との対談集)「もののけ姫」「出発点」(以上、徳間書店刊)、「折り返し点」(岩波書店)など多数がある。