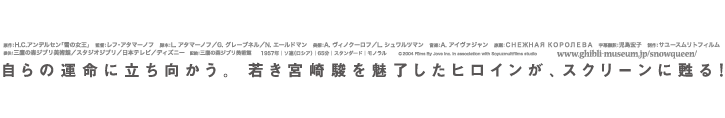Main Contents

夢の力を持った作品
シンガーソングライター 谷山浩子
50年前のロシアのアニメ映画というのがどんなものなのか、まったく知らなかった。想像もつかなかった。
少なくとも「うわ~、おもしろそう!」とは決して思わなかった。
もしかしてパラパラマンガみたいなもの? 静止画がよく見ると動いてましたっていう感じ? 退屈? 陰鬱? 厳格? 途中で寝ちゃう? 大好きな「雪の女王」が「なんじゃこりゃ」的びっくりアニメに大変身? などなど、 とっても失礼な心配をしながらディスクをトレイに乗せた。
で、どうなったかというと、最初のほう、カイとゲルダが屋根窓のあいだの小庭で遊んでいるシーンで、いきなり涙が出てきた。そしてそこから、ずーっと涙目のまま、息をするのも忘れるくらい夢中になって、最後までこの映画を見てしまったのだ。
なぜそんなに夢中になったのかって? まるでわかりません。こっちが教えてほしいくらいです。
…なんて言ったら話が終わってしまうので、少しは頭を使って考えてみよう。なんでこんなにいいんだろう、このアニメ「雪の女王」1957年ロシア版は。
子供のころから「雪の女王」は大好きな物語だった。最初は純粋に物語にはいりこみ楽しむだけだったけれど、おとなになってからは物語のテーマにも注目するようになった。
悪魔の作った鏡のかけらが目と胸にはいったカイは、雪が結晶のかたちにしか見えなくなる。その規則的で矛盾のないかたちを、何より美しいと思う。そして寒い寒い雪の女王の宮殿で、寒さを感じることなく、一日中氷のかけらを組み合わせるパズルに熱中している。あらゆる言葉を氷のかけらで作り出せるけれど、ただひとつ作り出せない言葉がある。それは「永遠」。
このカイの変わり果てた姿、ゲルダの呼ぶ声も耳に届かなくなってしまったカイの姿を、今の時代のわたしたちに重ねれば、「西欧近代主義に対する批判」というテーマを読み取ることもできる。科学者の究極の夢は、永遠を自分の手でつかまえることではないか?
また別のテーマ。ゲルダとの親密な日々から、花や、やさしい心の通い合いのようなものを拒絶して、乱暴な言葉と少年同士の競い合いを好むようになり、やがてどこかへ出ていったきり、行方をくらましてしまうカイ。カイを取り戻すために、行き先のわからない旅に出るゲルダ。そして長くつらい旅路の果てに、ついにゲルダはカイを救い出す。
これを、ひとりの人間の中で起きるドラマととらえることもできる。わたしの中にカイがいて、ゲルダがいる。女性性と男性性の分離。そして苦しんだ末の再統合。自己実現の長い旅。
…などと解釈をしてみて、それはそれで悪くはないんだけど、なんだか違和感があるなと思う。そして、気がつくのだ。物語からテーマを読み取ろうとする、あれこれ頭で解釈して「コレはアレの暗喩かも」なんて悦に入っているわたしは、まるで氷のパズル大好き少年、カイそのものではないか!
わたしが「雪の女王」を好きなのは、物語が近代主義の批判になっているからでも、自己実現のドラマだからでもない…いや、それは意識の奥の奥のほうではちゃんと理由なのだろうけど、そんな風に言葉で説明できるようなことが、 この物語の魅力の中心なのではない。
言葉で説明できることは、言葉で説明すればいいのだ。物語にとっては、 テーマは骨であり、網であり、本体ではない。本体は…本体は、水か空気か音楽みたいなものだ。網ですくおうとすれば、こぼれてしまう。
その、水か空気か音楽みたいなものとは、「イメージ」だろう。たぶんそうだ。夢のようなイメージのひろがり。「雪の女王」という物語の紡ぎ出すイメージは、鮮烈で強い磁力を持っている。美しいとか不思議とかいう言葉で簡単にかたづけてしまうことのできない、魔法のような磁力だ。
その強い磁力を持ったイメージを、1957年ロシア版「雪の女王」は、あっと驚く見事さでまるごと映像にすくい上げている。少なくともわたしの目にはそう見える。どうにもこうにも、そうとしか見えない。この思いをどう言葉にしたらいいのか。「小さいころわたしはこの映画の中で暮らしていました」とでも言えばいいか。それとも「これはわたしが見ている夢です」…。
この映画にわたしが惹きつけられた理由を、思いつくまま列挙してみる。
まず、色だ。
なんという美しい緑、美しい赤。
暗い色調の緑がため息出るほど美しく、この緑だけあれば他に何の色もいらないくらいなのに、そこに、これ以上ないというほど似合いの赤が寄りそう。たとえば厚いガラスを重ねたような緑と、おばあちゃんの古いコートのような赤。それ以外の色もすべてが魅力的で、今の世の中でどこへ行ったら見られるんだかわからないような、暖かくくすんで、どこか浮世離れした色合い…もしかしたらフィルムが褪色してこうなったので、もとはもっと鮮やかな色だったのかもしれないけど、それはどっちでもいいのだ。今見ることのできるこの色が、わたしは好きなのだから。
それから、動き。
やわらかく絶えまなく、波のようにゆるやかに動きつづける人物や動物たち。官能的なやわらかさ。絶えまなく動く彼らの背後で、音楽もまた絶えまなく動いている。波と波。重なりあい、溶けあい、離れてはまた寄りそう波と波。
音楽は、物語やシーンを説明しない。音楽も映像と同じように、そこにあり、動きつづける。そしてもうひとつの映像となって、物語に立体的な奥行きを作りだすのだ。
印象的なシーンは数え切れないほどあって、ひとつひとつ挙げていたら切りがないけれど、少しだけ挙げるなら、まずカイとゲルダの遊ぶ空中小庭園、その上にひろがる空(わたしの涙目スタート地点だ)。
それから、少年たちがそり遊びをする冬の街。
ゲルダの乗ったボートを運んでいく川と、飛び交うツバメたち。
花園の入口の小さな兵隊と、意外なほど大きな魔法使い(わたしは小さなころから、この花園の話がほんとうに好きだった。ゲルダを抱きしめて離さない、美しいまどろみの牢獄。そして花園の外、風の吹きすさぶ荒涼とした世界の恐ろしさ。ここを、たぶんわたしたちの誰もが知っているけれど、誰も言葉にすることができない)。
山賊の娘の部屋で、トナカイと鳩と娘が「知っている」「知っている…」と言い交わす、そのくりかえしの不思議さ。トナカイの「わたしは知っている」 という声の深い響き。
ゲルダを乗せて疾走するトナカイと、裂け目の向こうを伴走するトナカイたち。
吹雪の中で悲しげに「コートを!」「テブクロを!」「ブーツを!」「帽子を!」と叫びつづける、フィン人のおばさん。おばさんの姿が心に張りついて剥がれなくなってしまうほど、このシーンの印象は強い。
映画の冒頭で、案内役のオーレ・ルゴイエが物語を「夢」として紹介するのは、すばらしい導入だ。夢ほど人の心に近しいものはない。人の心に確かに存在する強大で広大な王国でありながら、これほど軽んじられ、忘れられているものもない。だけどどんなに軽んじても、忘れていようとしても、人は自分の夢から逃げることはできない。ひとりの人の夢の王国は、物理的存在としての宇宙より大きく、無限に、永遠に広がっているからだ。
雪の女王の物語は、ハンス・アンデルセンというひとりの人の夢であり、それに触れるわたしたちみんなの夢でもある。1957年ロシア版「雪の女王」は、そのことを(意識の上でか、または無意識のうちに)よく知っている人たちの作った、現実世界に出現した夢だ。21世紀の今、こういう夢の力を持った作品を作ることは、たぶん当時よりずっと難しいことに違いない。
谷山 浩子 (たにやま・ひろこ)
一九五六年、東京都生まれ。お茶の水女子大学文教育学部附属高等学校卒。一九七二年にアルバム「静かでいいな~谷山浩子15の世界~」でメジャーデビュー。現在までにアルバム三十七作品をリリース。NHK「みんなのうた」「おかあさんといっしょ」やCF、他アーティストへの楽曲提供、オールナイトニッポンを始めとするラジオ番組のパーソナリティも務める。映画「ゲド戦記」(宮崎吾朗監督作品)においては挿入歌「テルーの唄」の作曲を手掛ける。最新アルバム「フィンランドはどこですか?」(ヤマハミュージックコミュニケーションズ)では、中島みゆきとの初の合作となる「雪虫 Whispe」が収録されている。また、二〇〇八年三月二日には、デビュー三十五周年を記念して東京国際フォーラムCでコンサートが開かれる。
第一回 鮮やかな記憶 ─ バレリーナ 草刈民代
第二回 洗練されたロシア版アンデルセン ─ 児童文学評論家 赤木かん子
第三回 「雪の女王」の中にあるロシア的なるもの ─ 児新訳版字幕担当 児島宏子
第四回 夢の力を持った作品 ─ シンガーソングライター 谷山浩子