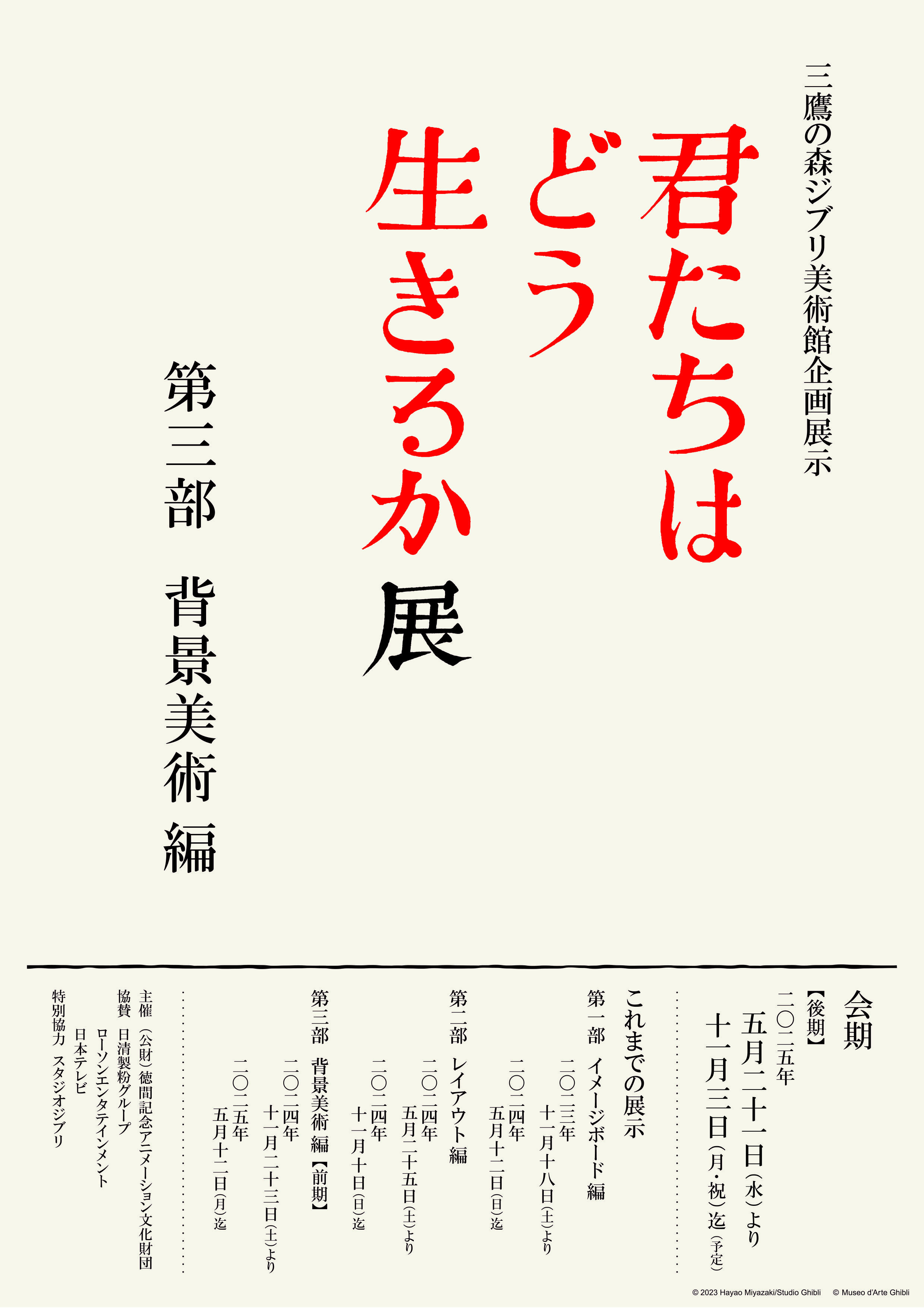西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.35 ぼくの妄想史【参】 ハントのひつじ
2013.01.29
ロンドンにあるテート・ブリテンのラファエル前派の部屋には、ウォーターハウスやミレイといった画家の作品のほかにも、絵が飾られています。今回取り上げるのはハントの代表作、"Strayed Sheep"(迷える羊)という一枚です。
ウィリアム・ホルマン・ハント(William Holman Hunt, 1827-1910)はロンドンに生まれ、1844年、ロイヤル・アカデミー・スクールズに入学。そこで、ミレイ、ロッセティらと出会いラファエル前派を結成した、近代英国を代表する画家です。作風としては、聖書から題材を得た宗教画をたびたび描き、その取材のために3度もパレスチナを訪問するなど、あいまいさを許さない学究的な一面があげられます。また、光の描写の研究に余念がなく、代表作である"世の光"というキリストを描いた作品の制作のために、数ヶ月にわたって夜の野外で絵を描き続けたなどのエピソードが残っています。また、ラファエル前派の作風のひとつとして、記号として絵の中に象徴的な物を描き込むこともあげられ、絵に込められたメッセージを読み解くことが行なわれてきました。
 "Our English Coasts (Strayed Sheep), 1852"
"Our English Coasts (Strayed Sheep), 1852"
ハントの"Strayed Sheep"はもともと"Our English Coasts"というタイトルで1852年に発表されたのですが、その後1955年に改題されたものです。光が全体にあたっていて植物に覆われたイギリスの海辺の断崖にたくさんのヒツジが戯れている絵です。崖っぷちでたくさんのヒツジが草を食べているのですが、脚をふみはずせば崖下にころげ落ちてしまいそうなのに、そんなことはおかまいなしに呑気に草を食べるヒツジたち。当時の英国の外国に対しての無防備さを揶揄した作品とも言われていますが、ヒツジ=人民だと考えると、足元の不安定さに気づかず日常を漫然と生きている現代人への警告とも取れる作品です。宮崎監督はこの作品を実際に見て、「夏目漱石の"三四郎"に出てくる"ストレイシープ(迷羊)"はこの絵から生まれたのか」と思ったそうですが、事実、漱石もこの美術館を訪れていることから考えるとあながち妄想とはいえないのではと思います。
 "The Hireling Shepherd, 1851"
"The Hireling Shepherd, 1851"
ただ、ダミアン・フラナガンという英国人が書いた『日本人が知らない夏目漱石』という著作では、"ストレイシープ"の由来は、ハントの"雇われの羊飼い"という作品ではないかと推論しています。こちらは、小川のほとりの草むらに横たわる恋人らしき男女、そのうしろにたくさんの羊が戯れている構図です。手前にはライラック(?)の花やリンゴなど記号らしき象徴となる物が意味ありげに描き込まれています。どちらかというと、男女の存在が目立つ作品なのですが、後方で一頭の羊が群れから外れて小川を渡ろうとしているところが描かれており、これが"ストレイシープ"を意味しているのかもしれません。
今となっては何が真実なのかは決められないのですが、ハントが羊という家畜になんらかの意味を込めて描いているのは事実でしょう。聖書に登場する羊は、当時のパレスチナ地方ではごく普通に飼われていた家畜でした。外敵に襲われても抵抗するすべを持たず、群れで闘うこともせず、羊飼いに命じられるまま行動するところから、神=羊飼い、人間=羊として、たとえ話に取り上げられるのですが、ハントの絵でもこれを現代人の象徴と考えるのは自然な気がします。
宮崎監督は、この"Strayed Sheep"については、さらにおもしろい視点から考察しています。「それにしても、油絵で日本の自然を描くのはとてもやっかいなのです。『迷える羊』の風景のように、湿度が少なく、はるかかなたまでキラキラしている風景は、日本にはありません。みどり、みどり、みどりです。」と。確かに、日本ではこのような草に覆われた海岸というものはなかなかお目にかかれません。日本のような高温で多湿な気候では、すぐに緑の低灌木に覆われてしまうからです。日本の自然が緑以外の色に覆われるのは、秋から冬にかけてのわずかな時期に限られるわけで、このことが日本の風景画に大きな制限をかけているというのですから、確かにユニークな視点だと思います。