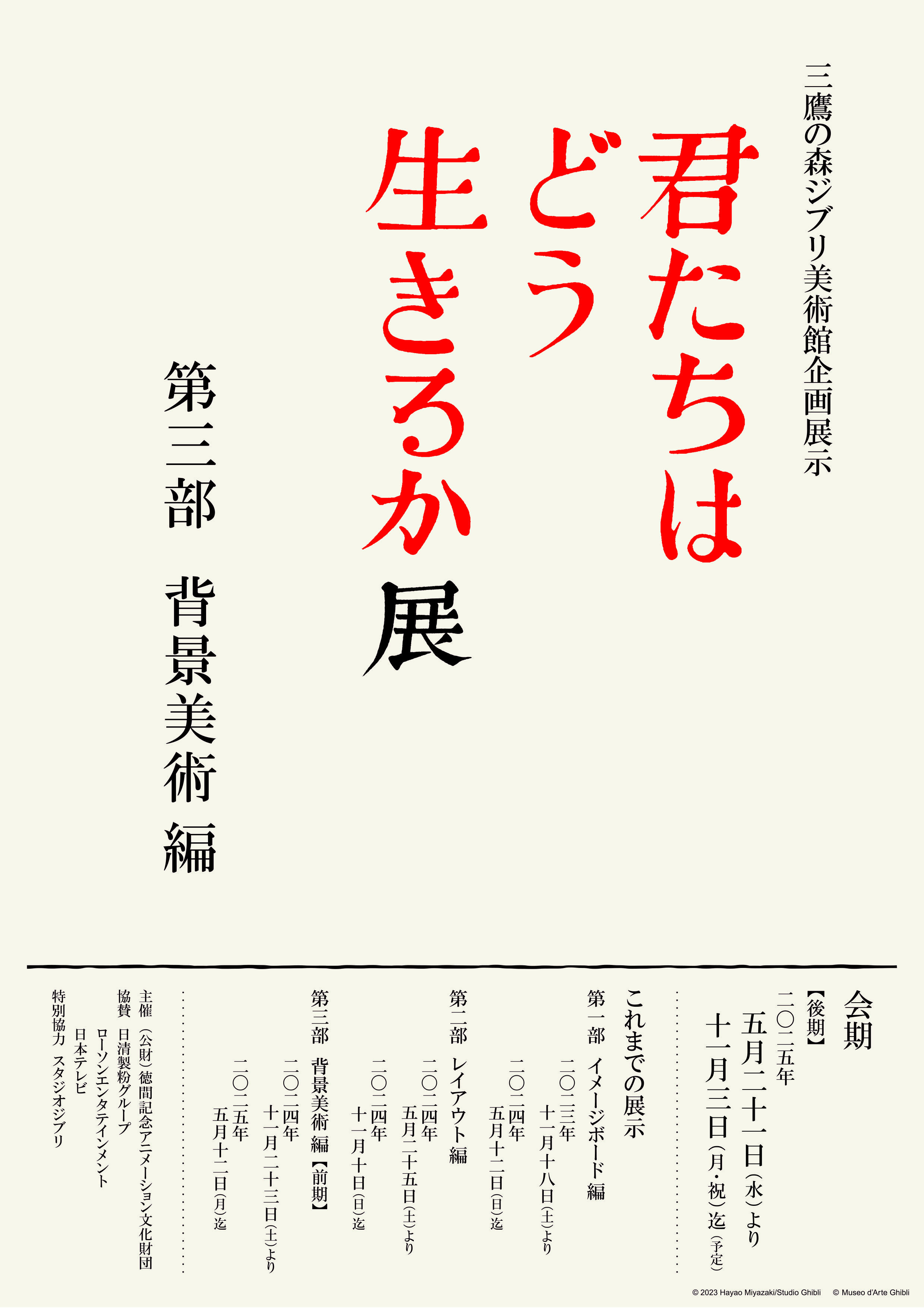西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.36 ぼくの妄想史【四】 日本で洋画がはじまる
2013.02.05
明治維新以降、洋画というジャンルの絵が誕生します。それまでの天然画材を膠(にかわ)で溶いた顔料ではなく、溶剤として乾性油を用いた油絵や水彩画のことを一般に洋画と呼ぶようで、日本画と違って輪郭線がないという特徴もあります(そう考えると日本でアニメーションの絵が受け入れられやすいのも、日本画に親しんできた伝統かもしれません)。これらの絵を日本に伝え、描き始めた画家のひとりが、今回取り上げる山本芳翠(やまもとほうすい、1850-1906)です。
山本芳翠は、岐阜県恵那郡の農家の息子として生まれました。北斎の絵に魅せられ画家になることを志し、京都で文人画を学び、中国に留学して本格的に学ぼうと上京したのが22歳のときでした。この地で五姓田芳柳(ごせだほうりゅう、1827-1892)の絵に魅せられ洋画に転向、美術学校などで学びながら、今度はフランスへの留学のチャンスをうかがいます。ただ、当時、一般人が海外留学するのはとても無理な話で、1878年、芳翠は密航に近い形でフランス行きの船にもぐりこんだといわれています。その船はパリ万博への展示を運ぶ船で、もう引き返せない洋上に出てから、事務局に雇ってもらえるように頼み込んだといいますから、芳翠の留学への情熱は大変なものでした。フランスでは、パリ国立高等美術学校に留学し絵画技法を学びながら、面倒見の良かった芳翠はたびたび日本料理をつくって同胞の留学生たちをもてなしたそうです。そんな中で出会ったのが、法律を学ぶために留学していた黒田清輝で、彼の絵画の才能を見出し、画家の道に進むように勧めたのも芳翠でした。
帰国後は、洋画家約80人が集まって「明治美術会」を発足し、年に2回の展覧会を開催、広く洋画の普及に努めました。本人は「今に黒田が帰ってくる。そうしたら日本の洋画も本物になるだろう」と語り、黒田清輝の帰国後は、一線を退き後進の育成に努めますが、晩年は舞台美術などを手がけ、56歳で亡くなりました。
そんな洋画の普及に努めた芳翠の代表作が、会場に写真が展示されている「浦島図」(1893,岐阜県美術館所蔵)です。

この絵、洋画の技法を使って日本の昔話の一場面を描いたものです。浦島太郎が竜宮城から玉手箱をもらって帰るところで、乙姫をはじめとする女性たちに見送られているシーンです。だれもが知っているお話の絵ですが、見るものには強烈な違和感を感じさせる不思議な絵です。空が妖しい雲に覆われているせいでしょうか。背後にそびえたつ竜宮城が立派な石城として描かれているせいでしょうか。それよりも奇妙なのは、登場する人物が、欧州の裸婦像のようにふくよかで色白でなまなましいことでしょう。なんとなくインドや東南アジアの宗教画のようにも思えます。この強烈な違和感となまなましさは、見るものを不思議とひきつけてしまいます。芳翠はわざとこのような違和感を描いたのでしょうか。
宮崎監督は、「日本人なら誰もが知っている物語に、新鮮な解釈を加えて、世間をあっといわせようとしたのです。」と解説しています。ヨーロッパの絵画では、宗教や神話をテーマにした絵画がたくさん描かれていました。この精神を日本に持ち込んだ芳翠は、題材を日本の昔話に求めることに挑戦したのではと思います。結果として、それは難しい挑戦で、一般大衆が持つ日本画と洋画の固定されたイメージをつき崩すことはできませんでした。記号化ではなくリアリズムに従って描かれた絵たちには、どこかあやしさや通俗性がまとわりつき、見るものの違和感を拭い取ることはできませんでした。このあと、日本の洋画は世界の潮流に乗って抽象画の方向へかじを切っていくことになります。
宮崎監督はさらに語ります。「それなのに、ぼくはこの絵に他人事ではない気分をかきたてられます。アニメーションで外国を舞台にした経験を思い出すと、『浦島図』の後輩だと思ったりします。」と。ヨーロッパ絵画と格闘した大先人として、山本芳翠の名は忘れてはならないのです。